コラムColumn
課長職の役割(その2)
2020/09/11

「課長もんカレ(しつもん経営研究会:発行㈱YCDI)」
課長職の役割は、新入やベテランの正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など様々な人員からなる所管部署について、業務目標を立て、全体の進行管理を行い、人材育成や労務管理も行いながら成果を出すことですが、同時に、プレーヤーとして部下職員の手本となるような役割も任されていました。
課長職の比較的大きな割合を占めていたプレーヤーとしての役割も、テレワークなど在宅等での勤務が進む中では、必要とされなくなる部分ではないでしょうか。
今後は、課題やその解決方法を自ら発見することができる自律した社員の育成が大きな役割となると思われます。
課長職の役割
2020/08/17

「課長もんカレ」
一般的に管理職の役割は、所管する組織の業務目標を立て、全体の進行管理を行い、成果を出すことであり、同時に人材育成や労務管理も必要とされます。
特に課長職の部下の構成は、新入社員からベテラン社員まで幅広く、年齢や能力には大きな差があり、正社員のみならず、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など様々です。
一方、テレワークなど在宅等での勤務が進む中で必要とされる社員は、課長職からの指示で働くだけではなく、課題やその解決方法を自ら発見することができる、自律した自己管理ができる社員だと思われます。
この様な時代に、改めて「課長職とは何か」を考えてみるため、日々の出来事を「課長」としての自分に問いかけてみるカレンダー方式の「課長もんカレ」ができました。(東京都社会保険労務士自主研究グループ「しつもん経営研究会」作成)
今後ネット販売を予定しており、購入先URLが決まり次第、改めてご紹介いたします。
Go Toキャンペーン
2020/07/20

(小笠原のパッションフルーツ)
Go Toキャンペーンの一つ、Go Toトラベルが7月22日から開始されます。
当初、8月に入ってからの開始予定でしたが、7月の4連休に合わせるため、開始日程の繰り上げを発表した途端、新型コロナ感染者数が急増し、特に東京都内では連日300人近い人数で、どこまで増えていくのか分からない状況です。このため、7月22日からのGo Toトラベルでは、東京都は対象地域から除外されてのスタートとなっています。
一方、出かける方も旅行先で感染するリスクと感染させてしまうリスクを心配しながら旅行に行くことに躊躇している状況もあります。冷え切っている旅行業界の業績回復のためには、必要なキャンペーンだと思いますが、新型コロナ感染症対策と経済を回していくことの両立の難しさを感じます。
これから先も様々なGo TOキャンペーンが始まりますが、離島など特に訪問が難しい地域の特産品を取り寄せることにより、その地域に想いを馳せたいと思っています。
レジ袋1枚3円の影響
2020/06/29

7月1日から日本全国のお店で使用されるレジ袋が原則として有料化されます。コンビニなどでも、会社によりその価格は多少異なりますが、袋の大きさにより特大5円又は4円、その他3円又は2円、すべての袋が3円などとなっております。
(近所のスーパーは以前から1枚10円で、ほとんどの人がマイバック等を持参しています。)
一方、紙袋や持ち手のない袋、厚さ0.05㎜以上の袋(繰り返し使用できるため)、環境への影響を配慮したバイオマス素材(植物等生物由来の物質で造られ、自然界で再生可能な素材)25%以上配合の袋などは有料化の対象外となります。
海ごみなどのプラスチックごみが自然環境に与える負荷を低減させるため、その使用を抑制する国の施策ですが、国内レジ袋の使用量は年間20万トン程度で、一年間に排出される廃プラスチック製品に占める割合は2%程度です。
経済的な面はもとより、スーパーのレジ袋のストックがなくなることによりごみ袋の購入が必要になる、コロナウイルス影響下でのマイバックの使用方法など課題もあります。
しかし、1枚数円のレジ袋が人々にマイバック等を持たせる習慣となれば、プラごみ問題への意識の変化、さらには環境にやさしいライフスタイル(新しい生活様式)への転換へのきっかけになると思います。
デジタルとアナログ
2020/05/22

非常事態宣言が延長された東京では、在宅でのテレワークや休校が続く学校でのオンライン学習など外出自粛生活が数か月続いております。
コロナ危機で浮かび上がった日本のデジタル対応の遅れですが、これを契機とした電子化・オンライン化の加速は、私たちの生活や職場環境、学校生活に大きな影響を及ぼしていくと思われます。
一方、一日中パソコン等で仕事をすることによる「デジタル疲労」や長期間、人と直接話をしないことによるメンタルヘルスの対策も重要になってきます。パソコン業務の疲労感は運動後の疲労感のような心地良さがありません。
その反動からか、例年より長く感じた今年のゴールデンウイークは、読書(本)やレコードによる音楽鑑賞などアナログな生活で、紙の感触やレコードの懐かしい音色に親しみを感じた期間でもありました。
今後も、自分で工夫しながら、両方のバランスを取った生活が必要になるのかも知れません。
非日常
2020/04/22

今年の桜のシーズンは早く始まり例年より長く続きましたが、全国に拡大された非常事態宣言の発出により、花見は自粛要請がなされ、ゆっくりと桜の花を愛でる環境ではなかったと思います。新宿や渋谷などの都心繁華街の休日も、人出は例年の80%前後の減となっているとのことで、自粛要請を守って買い物や飲み会等を控えている方も多いようです。
5月6日までは、職場は時差出勤やテレワーク等による在宅勤務、業種によっては休業自粛要請等に基づく臨時休業、学校は臨時休校など外出や人ごみを控える状況となっています。外出が難しい中で、時間の経過とともにマンネリ感とこの環境がいつまで続のかという不安感も出て来ます。
これまで働き方改革への対応で、ワーク・ライフバランス導入のための一手法となっていたテレワークの導入が、新型コロナ感染症対応のための出勤制限により、BCP対策として、急遽それも一斉にそうせざるを得ない状況となって来ました。
この状況の継続は、今後の社会の仕組みや仕事のあり方の転換となるかも知れません。
改めて復興五輪
2020/03/27

東京2020オリンピック・パラリンピックの延期で、3月26日に東日本大震災の被災地福島をスタートする予定であった「聖火リレー」も延期になりました。
「復興五輪」を掲げてオリンピック・パラリンピックの開催都市となった東京。新型コロナウイルスにより延期となった2020東京大会が、改めて開催される時には、「新型コロナウイルスに打ち勝った五輪」と呼ばれ「復興五輪」の言葉は薄れてしまうのでしょうか。
脱・24時間営業/年中無休
2020/03/09

24時間営業があたり前だったコンビニやファミレス業界での24時間営業の取り止めや、元旦から福袋を販売していた百貨店業界等での元旦営業の取り止めなどの報道をここ数ヶ月で見聞きします。人手不足や人件費高騰による経費削減、ネットの普及による客足の減少、働き方改革への対応など要因は様々だと思われます。
さらには、最近の新型コロナウイルス対策のための営業・出勤・外出抑制の影響により、休業や営業時間を短縮する店舗も増えています。新型コロナウイルス対策は一時的なものかも知れませんが、脱・24時間営業/年中無休の流れを加速させる起爆剤になるかも知れません。
経済への影響も心配されますが、テレワークの促進などこれからの働き方を改めて考える大きなきっかけになると思われます。
2020年のキーワード
2020/01/06
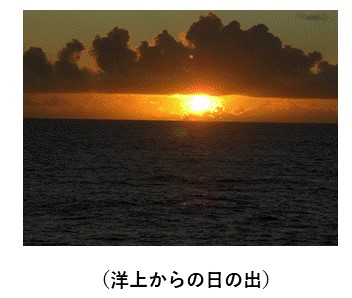
元旦からテレビや新聞などで使われていた言葉の中では、「東京オリンピック・パラリンピック」、「働き方」、「環境」の3つが多かったように思われます。
昨年のラグビーワールドカップでは沢山の外国人が訪日しました。東京オリンピック・パラリンピックはそれを上回る外国人の訪日や、日本全国から東京を中心とした大会会場がある都市への訪問など「人の流れ」がここ数十年の間で最大となると思われ、その流れの中で人と人との新たな「出会い」や新しい「もの」が生まれる可能性があります。
「働き方」も大きく変わると考えられます。昨年トヨタ自動車労働組合が、賃金原資の配分方法を組合員全員の基本給を一律に底上げするベースアップから、人事評価に応じて配分する制度の提案をしたというニュースがありました。労組も組合員横並びからの脱却を唱える中、オリンピック・パラリンピックを契機に「時差出勤」などによる働く時間帯や「テレワーク」などによる働く場所の多様化が広がり、働き方改革が進む中での「働き方」に大きな変化が出て来る可能性があります。
「環境」の面では、地球温暖化による自然災害への懸念とともに、7月からの「レジ袋の全面有料化」が環境への意識を変化させる契機になると思われます。国内レジ袋の使用量は年間20万トン程度で、一年間に排出される廃プラスチックの2%程度ですが、1枚数円のレジ袋が人々にマイバックを持たせる習慣となれば、プラごみ問題への意識の変化、さらには環境にやさしいライフスタイルへの転換への可能性が生まれます。
いずれにせよ、今年は様々な場面で、日本のいい面も悪い面も意識せざるを得ない1年になると思われます。
冬季休業のお知らせ
2019/12/06
歳末の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて誠に勝手ながら、12月28日(土)~1月5日(日)まで
冬季休業とさせていただきたくご案内いたします。
ご不便をおかけいたしますが、
社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所 代表 今井正美
